子どもの頃、夕暮れになるといつも気になっていたことがあります。
それは・・・
春、日中暖かな色に見えていた桜が夕暮れになると仄白く見えたことでした。梅雨時には、青いアジサイが発光しているように見えました。夏には、紅と白のオシロイバナが青白く感じ、初冬には桃色のサザンカが青白く見えました。
一方、冬の夕暮れには赤い椿は暗く見え、郵便ポストは黒く静まったように見えました。
子どもにとって、夕暮れは楽しかった一日が終わるようで、その心細さから風景も違って見えたのだと思っていました。
また夕暮れは、町全体がわずかに青く色づいて見え、魔物が降りてくる時のようで、足早に家に帰りました。
.jpg)
上の写真を調整して作成
〇
印刷の仕事に就き、色で悩むことが多くなり、色彩のことを一から学びたいと考えるようになっていきました。学校で学ぶ色彩は配色が中心で、実際に色を見る目を学ぶことはありませんでした。
『色彩科学事典』(朝倉書店 1991年刊)の中に「薄明視」という言葉がありました。この本は随筆風の短い文章で書かれており、大変読みやすく親しみやすい事典です。
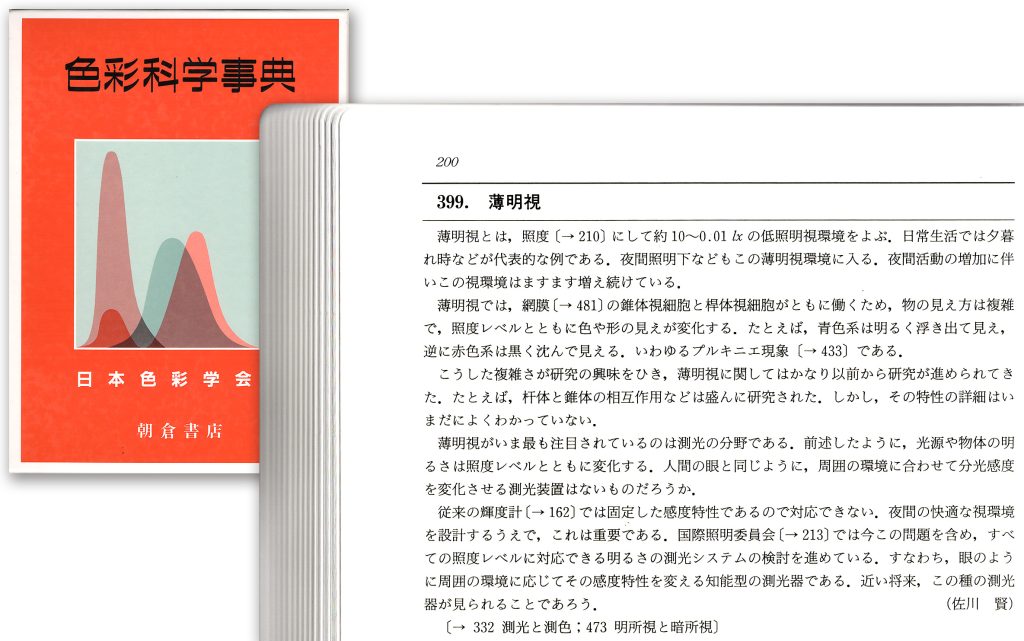
光を感じる目のセンサーには、明るいところで働き色を感知する錐体(すいたい)細胞と、暗くなると働きはじめる桿体(かんたい)細胞の2つがあります。夕暮れの時刻は、この錐体と桿体が複雑に働いていることが書かれています。その時の見えは「プルキニエ現象」[→433]の項に引き継がれていきます。
〇
「プルキニエ現象」とは、19世紀のチェコの生理学者プルキニエが気づいた現象です。
433の項には、「・・・並んで咲いていた赤い花と青い花が、昼間同じ明るさに見えていたにもかかわらず、夕方になると赤い花はかすみ、逆に青い花は明るく浮き出して見える現象に気がついた。花から発する光の成分は、昼と夕暮れでは大きな変化はない。単に光量が全体に低下しただけである。とすると、原因はそれを見る眼の方にあることになる。(中略)明るいところでは錐体が、暗いところでは桿体が働く。ここで2種の視細胞の色に対する感度が異なる。錐体は主に緑から赤にかけての中・長波長領域によく呼応し、桿体はむしろ短波長の青い光に高い感度を有する。」(色彩科学事典から引用。筆者は佐川 賢)
とありました。この感度の差が夕暮れには起きていたのです。
〇
小学生の頃、天気の良い日に陽のあたる校舎の屋上で体育をすると、前の人の白い体操着がまぶしく、ぼくは目を開けることができませんでした。その経験もあり、単に自分の目の感度がおかしいから、夕暮れに違和感を感じてしまうのだと思っていました。しかし、100年以上も前に、夕暮れの時間に起きる現象に気づき研究した人がいることを知り大変励みになりました。それからは、エッセイを読むように、この事典を楽しく読んでいきました。
この事典作りを提案され、編集委員長でもあった 金子 隆芳先生が色覚障がい(東洋インキのホームページからの引用)であることを、後に読んだ『色彩の科学』(岩波新書 1988年刊)で知りました。この本もぼくにとって大切な一冊になりました。
目のことを学べば学ぶほど、色に対する感性は人それぞれの個性と考えるようになりました。そして、この考え方が、その後の製版印刷の仕事で扱う色の捉え方の基準になっていきました。
難しい印刷物に携わると色で苦しむことが幾度もありました。原稿に写っていない(描かれていない)色を求められる時もありました。しかし、そのつど〝この人はこう見えているのだな〟〝色にはこの人の想いも含まれているのだな〟そして〝自分と違うのは当たり前〟と受け容れていると、自然に仕事はうまく収まっていくことが多かったです。(2023年1月)
