小野千世さんの文章教室で発表した「フレンズ」の書き出しは、毎日がはやく過ぎる大人の時間と、一日を長く感じる子どもの時間、その違いからでした。
違いは、日々の中にある驚きと疑問そして発見で心がどれだけ動いたかの違いでした。この心の動きがトキメキであり、その密度が一日の時間の長さを決めていました。
〇
仕事と生活が安定してきた時期に合わせ、トキメキを感じることは少なくなってきていました。そのような時に、トキメキをくれたのが「フレンズ」の6人でした。この人たちのことを、自分のことばで書いておきたく、文章教室のテーマにしました。自分の書いた文章を、教室で発表し、小野先生から赤字とエール(花丸)をもらうことで、客観性を持たせることができました。
〇
あらためて写真を並べてみました。共通点は元気なことと明るさ、そして戦争の時代を生き抜いてきたことでした。

ハンス・シュトルテさんは、ドイツから日本に着いて間もなく赴任した広島の教会で、原爆に遭遇しています。しかし、自分の置かれた境遇を前向きに受け入れ、ドイツで培ったワンダーフォーゲル精神で高等学校の山岳部の少年たちを育てながら、丹沢夜話を採取していきました。


多川精一さんは、高校を卒業して就職した陸軍参謀本部直属の東方社で、戦争でおかしくなっていく大人を見てきました。戦時下に二十歳を迎えています。その時培った反骨精神を最後まで失うことなく、印刷文化を見守っていきました。


坂本恵一さんは、戦後軍国少年から一転し、働き始めた印刷会社で反戦運動に身を投じて投獄されました。そして、バイタリティを失うことなく、製版レタッチ技術に光を当て、レタッチのおもしろさを語り続けていきました。
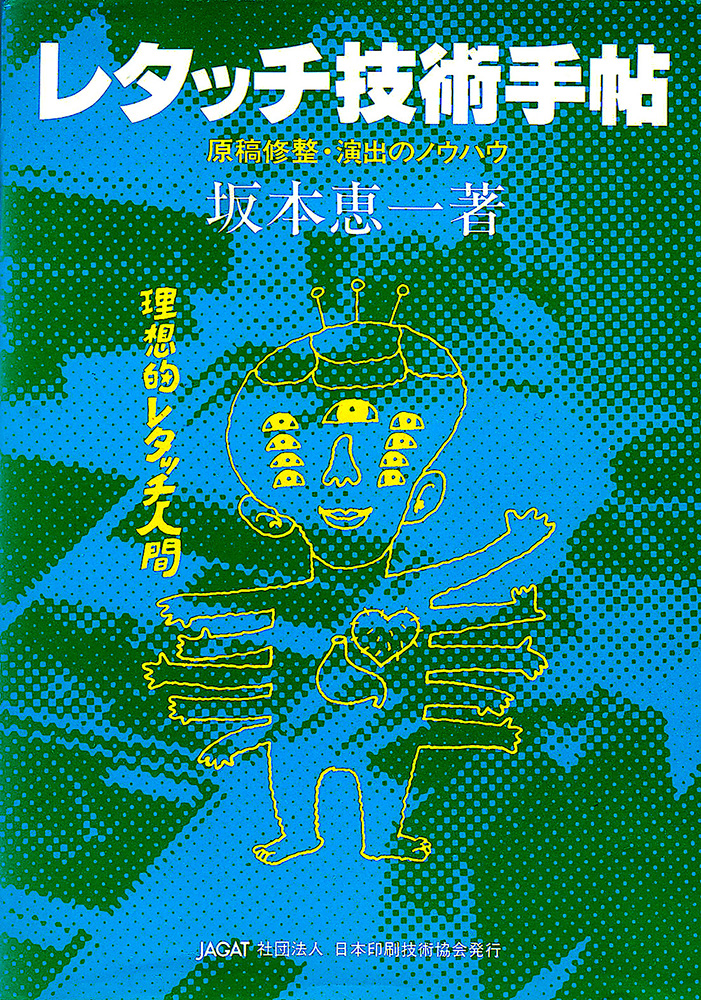

岡田勝司さんは、空襲で壊された橋の鉄骨にしがみ付きながら、川を渡った子ども時代を経験しました。逞(たくま)しい生命力を職場の同僚や仲間たちに与え続けてくれました。
*岡田さんに関する文章は掲載していませんが、岡田さんはがらんどうの駐車場に製版スキャナの作業場を一緒に作った盟友です。
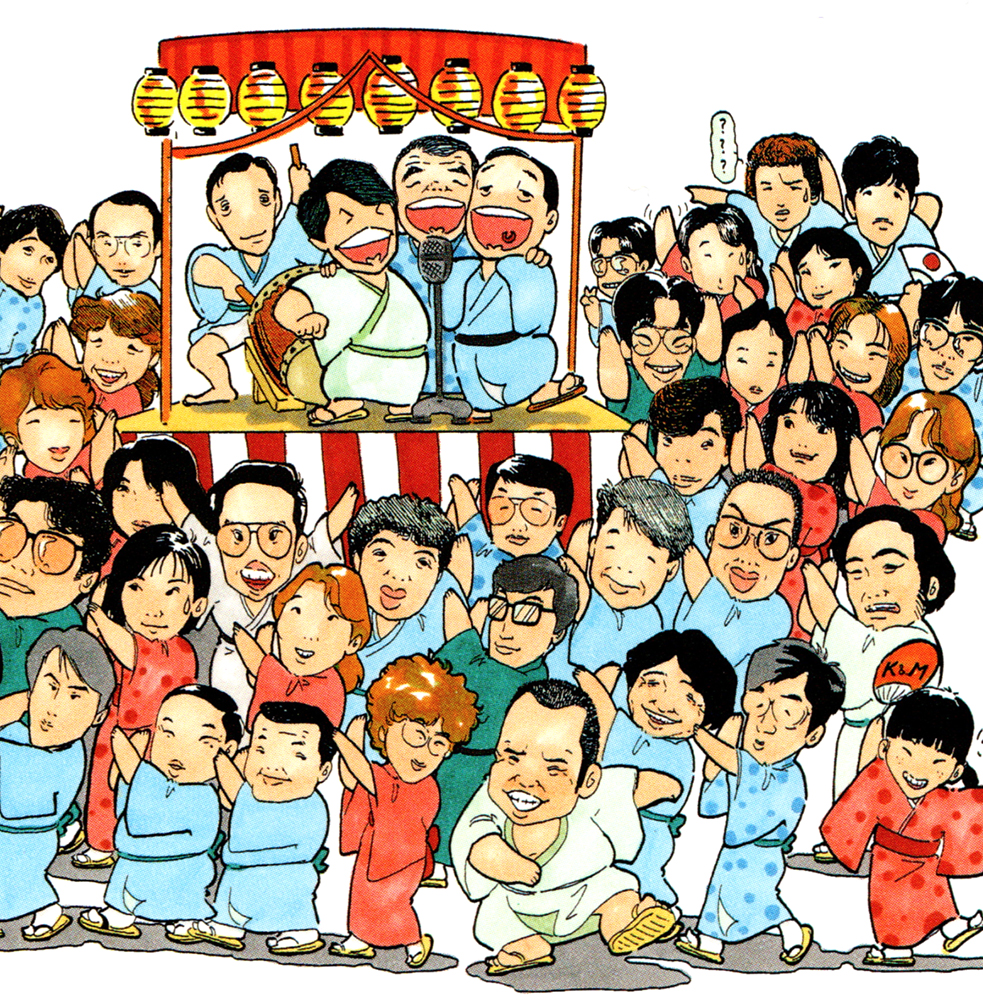

平野武利さんは、終戦の年に大学を卒業し、焼け跡に残った製版カメラの撮影現場にも怯(ひるむ)ことなく働きはじめ、生涯写真のおもしろさを伝え、追求続けていきました。
.jpg)

武市八十雄さんは、学友との志を受け継ぎ、物資の少ない戦後の中で子どもの本の出版を続けていきました。武市さんが育てた至光社は、現在も美しい絵本を出版し続けています。
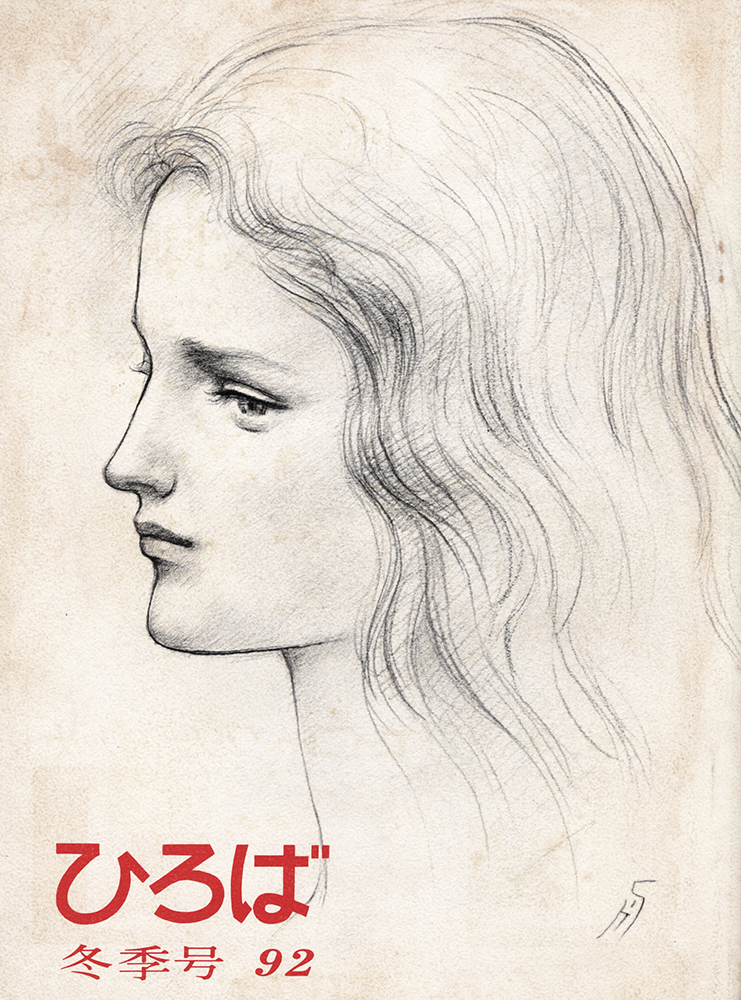
「明るさ」の後ろには、それぞれの戦争がありました。そこには、死の予感と空腹の中で、一日一日を噛みしめて生きていく時代であり、不安の中にも驚きと発見を感じる日々であったと思います。
〇
もうトキメキのお礼を返すことはできません。その中でぼくができることは、6人の足跡をさらに深く掘り下げていくことだと考えています。そこには、まだたくさんのトキメキが埋まっていると思います。それを掘り下げていくことがぼくができるお礼であり、いつか出会えることを信じています。
「チカちゃんの友達は、お年寄りばかりだね」と言われたこともありました。しかし周囲にいたどの人よりも、若々しくこの人たちは生き生きとしていました。いつか、この人たちに少しでも近づいていけるよう、トキメキを絶やさないよう歳を取りたいと思っています。(2022年9月)
